カキモリが Metal nib や Pen nib などのつけペンのシリーズを作り始めるきっかけにもなった、思い入れの強い書く道具。それが Glass nib です。

明治時代〜昭和中期頃まで日用品として使われていたというガラス製のペン。今ではガラスペンと聞くと工芸品で高価なものがイメージされますが、当時と同じように気軽に使えるガラス製のペンを作ってみたい、という思いが Glass nib を作り始めた背景にありました。
そうして2019年に発売したガラス作家・深澤亜希子さんと作った Glass nib は、デジタル社会の現代だからこそ、懐かしさや書くことの楽しさをより伝えてくれる道具となり、私たちが想定していたよりもずっと人気のある商品となりました。

それから、2021年に現在のつけペンシリーズを発売してからというもの、Glass nib を使ってみたいというお声はさらに世界へ広がっていきました。
Glass nib をもっとたくさんの方に届けるために、作家さんという枠から広げて、ガラス製品を作る工場や製作所と作ることができたら —— そして色々なガラス工房を探す中で、これまでの繋がりの中からご縁があり出会ったのが、関谷理化さんと TATSU GLASS さんでした。お話をする中で、ガラスペンを作れる職人さんがすでにいるとのことで、開発を受け入れてくださいました。
関谷理化は、清澄白河でビーカーやフラスコ、試験管などをインテリアとして提案している『リカシツ』を運営する、昭和八年創業の理化学問屋。TATSU GLASS は、関谷理化の関連会社で、1967年に創業した理化学ガラス製作所。4代に渡りビーカーなどの理化学品を中心にものづくりを行なっている町工場です。
TATSU GLASS は江東区に工場を構えており、カキモリからも近い場所。 せっかくなので、作っている様子を見に行かせていただくことに。

今回の開発は、普段ガラスペンを量産していない TATSU GLASS にとっても新しい挑戦だったようで、ガラスペンを作れる職人さんが中心となり試行錯誤しながら Glass nib の制作方法を考えてくださったのだそう。

使用しているホウケイ酸ガラスは、丈夫で耐熱性に優れているため、理化学品にはよく使われる素材。火から外すとすぐに固まり始めてしまうため、作る時は1300度〜1500度ほどに熱するバーナーが常に一緒です。
まずはガラスの棒からベースとなる土台を作っていきます。

次に、作った土台の端に、溝をつけるためのガイドとなる小さな丸をつけ、続いて溝を付け足すように加えていきます。


そして温めながら少しずつ引き伸ばしていき、Glass nib の細さに。

丁寧にサイズを測りながら調整し、いよいよ切り離す工程へ。 書き心地にも影響するため、中心を取りつつ切り離すこの工程が一番緊張する瞬間なのだそう。



そして今度は、低温で「アニール処理」という歪みや割れを発生しにくくする工程へ。小さなペン先にも手間を惜しみません。

最後にペン先の研磨をして、ようやく金属パーツと繋ぎ合わせ、完成します。

カキモリの要望を見事に叶えてくれた、TATSU GLASS さん。 普段は全く違うものを作る製作所と書く道具を開発することができたこと。改めて、素材のことを熟知した確かな技術が残る日本のものづくりの豊かさを感じた挑戦となりました。

作家のものづくりから、町工場へ。日本のものづくりの可能性が、Glass nib を通してさらに広がりました。 かつては当たり前のようにたくさんの職人によって量産されていたガラスペン。それから万年筆へ、そしてボールペンへと、主要な筆記具が変わる中で職人は段々と減っていき、今では限られたガラス作家さんが作るものになりました。 そんな中で今回、関谷理化さん、TATSU GLASS さんと出会い、一緒にものづくりをしたことで、ガラスペンをつくる技術を残していく可能性が見えたことや、そしてさらに新しい職人さんへの技術継承へと繋げる道筋を作れたことは、私たちにとって大きな一歩です。
深澤さんが作るこれまでの Glass nib も、今回新たに生み出した Glass nib も、どちらも大切に、さらにたくさんの方へ届けていきたいと思います。













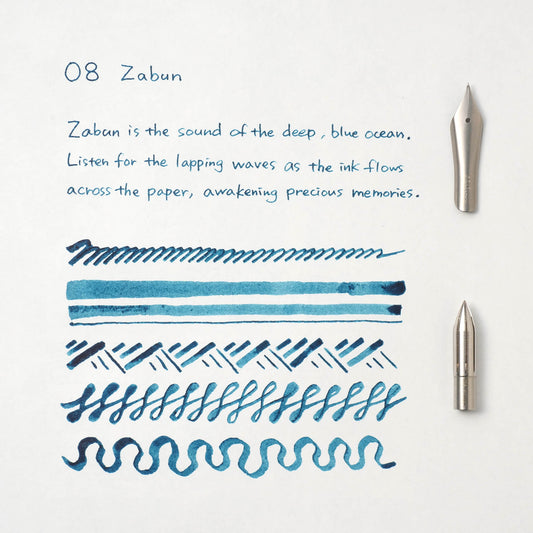

![百年先の誰かもきっと、[br/pc]「インクびん」の愛おしさにほほえむ[br/pc]第一回](http://kakimori.com/cdn/shop/articles/OH1_1918.jpg?v=1760603426&width=533)